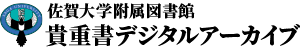洒落本の解説
江戸時代、享保(1617-1636)中頃より天保(1630-1843)頃まで行われた、戯作小説の一ジャンル。主に遊里を舞台とし、そこでの一昼夜の遊びを通して、遊女や客の姿を滑稽に描き出したものが多く、遊里短編小説とも説明される。
洒落本の体裁
洒落本の書型は、小本という、極めて小振りな書型が主流である。小本とは、半紙を半分に切ってそれを二つ折りにした、およそ縦16〜17cm、横11〜12cm程の書型で、現在の文庫本より少し大きめのサイズである。表紙の色は薄茶色のものが多く、このような外見から、洒落本を「蒟蒻本」とも呼ぶ。また、中本仕立てのものや、数は少ないが半紙本仕立ての洒落本もある。中本は、縦約19cm、横約13cmで、現在の新書よりも一まわり大きいサイズ。半紙本は、小本の二倍の大きさで、縦約24cm横約17〜18cm程。中本仕立ては、初めからこの形に仕立てられたものもあるが、元々小本仕立てで出版したものを、再版や改題して出版する場合などに、中本に仕立直して出版されることも多く、市場コレクションにおける中本仕立ての洒落本は、後者の事情によるものがほとんどである。
次に分量だが、一巻一冊で40丁〜50丁(1丁は2頁)というのが平均的。後にはシリーズ物も出たが、1冊読み切りが普通である。
洒落本の展開
洒落本の嚆矢とされるのは、享保十三(1728)年刊『両巴巵言』である。これは、吉原の情景や風俗を漢文で記し、それに細見(案内書)を附したもので、これが好評だったとみえ、『史林残花』(享保十五)、『南花余芳』(同十八)といった漢文体の戯文が続けて刊行された。これらは、当時の中国趣味流行の波に乗って日本に輸入された、中国の遊里や遊女を紹介した小冊子(艶史)を真似て、当時の漢学生たちが余技として手がけたものであった。その後この形式は上方で流行し、次第に漢文だけではなく和文をも用いて作られるようになる。
宝暦(1751-1763)頃になると、再び江戸でも、知識人たちによる、有名な漢籍や古典をパロディ化した洒落本が相次いで刊行された。『跖婦伝』(宝暦三年刊、泥郎子作)は、盗賊の跖が孔子を論破する『荘子』「盗跖篇」を、夜鷹のお跖が吉原の太夫高尾を論破する、という具合にパロディ化し、末尾に附した色説は『老子』の大道をそのまま色道にとりなしたものである。『跖婦人伝』の作者泥郎子は、幕臣山岡浚明であり、この作品の序を記した寛延二(1749)年には、西丸小姓組を勤めていた。また、『異素六帖』の作者中氏嬉斎は、漢学者で書家でもあった沢田東江である。
この宝暦頃には、小本仕立てで茶表紙という、いわゆる洒落本の外見は定まっていたが、洒落本が会話体の遊里短編小説としての形を調えたのは、明和七(1770)年刊の『遊子方言』からであろう。
遊客を、通・半可通・野暮と類型化し、野暮かと見えた人物が実は通で、通を気取った半可通が笑い者になる、というパターンはこの『遊子方言』に始まる。洒落本が別名「通書」と呼ばれるのもこうした内容によるものであろう。
『遊子方言』の、会話体で通・半可通・野暮といった類型化した人物を描く滑稽な遊里小説、というパターンを踏襲した作品が安永〜天明(1772-1789)にかけて続々と現れる。そして、洒落本の代表的作者山東京伝を輩出したこの時代こそ、洒落本の最盛期といえよう。
『通言総籬』『古契三娼』『傾城買四十八手』などに代表される京伝の洒落本は、遊里に通じた彼らしい洗練された感覚と精緻な描写で世に歓迎され、次々に追随作を生むことになる。
しかし、寛政改革に伴う出版取締りにより、京伝は、寛政三(1781)年に洒落本出版の咎で筆禍を受けてしまう。このことが大きなきっかけとなり、急速に勢いを失った洒落本のエッセンスは滑稽本や人情本にそれぞれ受け継がれ、洒落本自体は次第に下火となっていった。
叢書
洒落本の叢書としては、『洒落本大成』(29巻、補巻1、中央公論社、1978-88)が刊行されている。
(九州大学大学院 勝野寛美)