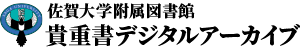扇面の解説
現在われわれが手にすることのできる開閉自在な扇は、数少ない日本の古代の創造品であり、当時より日本の輸出品として、中国や韓国へも広がり、そして後代にはヨーロッパへと広まっていたものである。
ところで、この扇という文字は、中国ではうちわ(団扇、円形の団扇(だんせん)と菱形の方(ほう)扇(せん)とがある)のことをいい、日本では、おうぎ(扇、いわゆる扇子(せんす)のこと。ただし、扇子は、中国明代の呼称が、日本で広く用いられ、扇全体の呼び名となったもの)を意味する文字となっていることは説明するまでもないであろう。では、この日本における扇の創造がいつごろだったかというと、9世紀中、あるいはそれ以前の平安朝極初期と考えられる。奈良時代にすでに在ったとの説もあるが、それは木簡の誤認の可能性が高く、日本独自の扇は、むしろその木簡に着想を得て成立したものではなかったかと考えられている。
はじめに出現したのは、檜木の薄板を20から30枚程度編綴して作られた檜(ひお)扇(おぎ)で、宮廷における礼服に欠かすことのできない装身具の一つとなり、男子用の白素地のものと女子用の装飾性の強いものとがあったことが知られている。男女共に、冬期に専ら用いたので、この檜扇は別に冬扇とも呼ばれた。この檜扇に対して、紙扇もほぼ同じ頃に出現したのだろうといわれているが、いま一つ確証は得られていないようである。紙扇は、扇の骨に地紙を貼って作られたものであることにより、「かみはり(紙貼)」の扇と呼ばれたのであるが、この「かみはり」が「こうはり」と音便化し、やがて、「かわほり」となり、「蝙蝠(かわほり)扇(おうぎ)」と呼ばれるようになったと考えられている。そして、この紙扇は、専ら夏に用いられたために、夏扇と呼ばれることになる。
次に、扇を構造的に見てみると、檜扇は、長さ30糎以上、幅約3糎以上の檜または杉板の上部に2ないし数孔を、また下部に要(かなめ)を通す1孔を穿ち、これらの孔を用いて20から30枚を編綴し開閉自在にしたものであるのに対して、紙扇は、竹または木・鯨髭・鉄などを骨とし、その上に紙・絹などの扇地紙を貼って、開閉自在としたものであり、構造的には檜扇も紙扇も、同じであるといってよい。だが、扇を開いた形の扇面、つまり要(かなめ)を下に置いて90度から120度、あるいは180度近くまで開いた時にできる形が、いわゆる扇面ということになるが、この扇面の形は、檜扇と紙扇では大きく異ったものとなる。檜扇の形は、全面が凸凹の板で、要から円周の外縁までの全てが面となり、そこに絵などが描かれるが、紙扇の場合は、要に近い扇の骨のみの、骨の長さの3分の1に相当する部分は、紙面にはならない。したがって、紙扇の場合は地紙の同心円の上弦と下弦とでもって限られた、扇形の平面ということになる。この2種類の異った扇面には、その出現このかた、文字、あるいは絵が描かれ続けてきたのである。発生時においては、純粋に服飾儀礼のために、あるいは、実用としてのメモ的書き付けのために用いられたと考えられるが、次第に装飾性を増し、芸術的な絵画や詩歌・文章もが書かれるようになって、扇面があたかも芸術表現のための画面として認識されるようになってくる。その認識が一般向となり認められてくると、扇の実用性から完全に離れたところで、純粋な芸術表現のためのキャンバスとしての扇面が求められることとなり、扇形の料紙を最初から別途に作製し、そこに絵画や詩歌・文章を書きつけ、あるいは書の腕を競うという、いわゆる扇面の芸術世界が生まれてくることになったのである。ただし、この2種の扇面は、それぞれ別種の扇面として、その異った独自の形を芸術表現の空間として最大限に生かすべく、それぞれ別の方向をたどっていくことになる。
本図書館が所蔵している市場直次郎コレクションの扇面の中には、残念ながら檜扇は所蔵されていない。その全てが、江戸時代初期から明治・大正時代にかけての紙扇(蝙蝠扇)であるといってよいが、その中でも、中心的に集められたものは江戸後期から幕末・明治初期の文人の書画であったといえる。ということで、以下に、扇面、それも紙扇の美術史的な展開の概略を述べておくことにする。
平安時代中期には、盛んに大和絵や唐絵が描かれていたことが清少納言の『枕草子』や、『源氏物語絵巻』によって知られるが、この時代を代表する扇面として現存するものは有名な四天王寺扇面写経帖である。料紙に扇面の型で、絵画の最初の輪郭は木版によって刷られ、文字が墨または金泥で書かれ、金銀砂子がほどこされている、目にもあざやかなものである。
室町時代初期(1328-1391)には、日本から輸入した扇に工夫を施した中国産の扇が日本に逆輸入され、日本の紙扇は、その影響で大きな変化を起こすことになる。それまでの日本扇は、片面に地紙を貼っただけであったが、中国の扇、唐扇は、両面から地紙を貼ったものであった。この製法が日本でも取り入れられ、末広(すえひろ)(中啓(ちゅうけい))・雪洞(ぼんぼり)・沈(しづめ)折(おり)という、現在の扇の基本的な形が出来てきたのである。末広は、地紙が旧来の倍の厚さになるため、畳んだ時に先が開いているものであり、雪洞は、真直ぐではあるが先端がやや開いているもの。沈折は、骨を薄くし、親骨の先端を内側に曲げて、先が開かないようにしたもので、現在、われわれが普通に用いているものである。この三種の紙扇が、近世の末にいたるまで、朝廷・公家・武家や諸芸能・茶道・華道・祭、その他諸々の分野において、それぞれの流儀に従って形が定められ、社会生活上の必備品として、多用されることになる。
明治時代に入ると、ヨーロッパで、唐扇を模して作られていた欧州扇が日本に輸入され、それをさらに模倣した貿易扇が流行し、現在に至っている。
扇面が広く庶民に受け入れられ、社会のすみずみにまで、むしろ日常の必需品として行き渡ってくるのは、江戸時代も後半になってからである。江戸時代初期の俵屋宗達工房の扇は、現在も扇面の雄といわれるものである。絵画史上極めて重要なものであるが、その扇面は、華麗に絵巻物の一場面を描いたもの、たとえば源氏物語の夕顔の巻などといったものが多く、庶民に広く愛好されたといっても、一部の富裕な階層に限られていたというべきであろう。だが、江戸時代後半になってくると、著名な文人や絵師などの書画会などが盛んに行われ、その書画会などの席において、即座に書画や詩歌を認める席画の習慣が扇面にも定着し、広く人々の需要に答えることになる。また一方では、書物の出版元で、扇の地紙や有名な絵師や文人・作家の自筆の扇面を販売するようになった。江戸の山東京伝や式亭三馬の場合は、自分の店で、客の注文に応じ販売していたことが知られているが、曲亭馬琴の場合は、扇面の潤筆料を定めた上で、江戸では神田通鍋町の柏屋半蔵の店で、また大坂では心斎橋筋の河内屋太助の店で、注文をとってもらい、一定枚数の注文がたまった折に、一度に潤筆し、それをまた、それぞれの店で売捌いてもらうという形をとっていたことが、馬琴の書簡や『馬琴日記』などで知られる。
今回紹介する市場直次郎コレクション扇面100点の内容を、分類項目に従って示せば、およそ以下のごとくである。
1 九州の文人達の書画
1)佐賀県 2名 2面(古賀茶渓、武富?南)
2)長崎県 2名 2面(高島秋帆、鐵翁祖門)
3)福岡県 7名 9面(二川相近、壇東郊、吉嗣拝山、幻庵曇榮、三苫雷首、吉嗣鼓山、原采蘋)
4)熊本県 1名 2面(豪潮寛海)
5)大分県 7名 7面(平野五岳、後藤碩田、田能村直入、広瀬旭荘、田能村竹田、廣瀬青邨、劉石秋)
2 漢詩 19名 19面(篠崎三島、菅茶山、斉藤拙堂、大橋訥庵、立原翠軒、東久世通禧、河野鉄兜、大窪天民、東條琴台、菊池五山、後藤松陰、南源性派、皆川淇園、江稼圃、大槻盤渓、梁川紅蘭、篠崎小竹、頼杏坪、佐久間象山)
3 和歌 10名 10面(千種有功、岡山高陰、久世安庭、伴蒿蹊、深川梅女、加茂季鷹、荷田蒼生子、大江廣海、清水濱臣、近藤芳樹)
4 狂歌 6名 6面(手柄岡持、紀定丸、川柳久良岐、狂歌堂真顔、大屋裏住、拙斎)
5 俳画 3名 3面(栗本玉屑、晋万和、森寛斎)
6 絵画
1)狩野派 3名 3面(狩野永納、狩野周信、狩野永岳)
2)土佐派 2名 2面(土佐光貞、土佐光孚)
3)住吉派 1名 1面(不詳)
4)文人(南宋)画 10名 12面(浦上春琴、池玉蘭、韓天壽、紀梅亭、中西耕石、安田老山、与謝蕪村、奥原晴湖、大沼枕山、大岡雲峰)
5)円山派 7名 8面(円山応震、長沢蘆雪、西村楠亭、月?、谷口月窓、吉村孝敬、山口素絢)
6)四条派 6名 7面(大西椿年、柴田義董、横山清暉、岡本豊彦、松村景文、柴田是真)
7)浮世絵 2名 2面(英一蝶、1名不詳)
7 書 2名 2面(山内香雪、市川米庵)
8 記念扇 3面(玉壺、横綱常陸山、1名不詳)
市場コレクションには、すでに述べたごとく、檜扇は蔵されていないが、扇骨のある扇面52扇、未表装の扇面まくり、中国の団扇などを含め、総数508点が所蔵されている。今後、整理・補修を終えたものより順番に、紹介していくことにする。
[参考文献]
中村清兄著『扇と扇絵』
河原書店 昭和44年刊
市場直次郎『ふるさと扇面譜』
西日本文化協会 昭和62年刊
(2004/03/29文化教育学部教授 井上敏幸記)