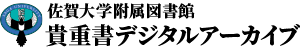大津絵節の解説
大津絵節は、江戸時代後期から明治時代にかけて全国的に大流行した、三味線伴奏の娯楽的な短い歌謡で、宴席の座興や寄席で歌われた。現在の研究では、都々逸(どどいつ)・とっちりちん・二上り新内・さのさ・かっぽれ・奴(やっこ)さんなどとともに、俗曲の一つとされている。
大津絵節の名は、近江国大津の追分・大谷あたりで売られた庶民の絵「追分絵」が、東海道を往来する旅人のみやげ物として喜ばれ、全国に「大津絵」の名が知られるようになったものであるが、その画題をよみ込んで、元禄も終りのころ(1700)から大津の遊里柴屋町の遊女達が唄いはじめたことによる呼び名であると考えられている。
ところでこの大津絵と呼ばれる絵の起りは、寛永年間(1624~1644)までさかのぼるとされているが、文献上最も古いものは、寛文元年(1661)刊の『似(じ)我(が)蜂(ばち)物語』に載る「天神の御影」を「大津あはた口のへんにて売」るという記事であるが、初期の頃は、この「天神」や「十三仏」「来迎阿弥陀」など、庶民の日常の礼拝に用いられた図柄がほとんどであったと思われる。元禄4年(1691)に芭蕉が「大津絵の筆の始めは阿仏」と詠んだのも、このことを物語っているといえよう。
芭蕉の時代、即ち元禄前後からは、世俗的な画題も登場し、その戯画的な世相風刺の、ユーモラスな漫画化された図柄に人気が集まって、仏画は次第に姿を消していくことになる。100種にも達したといわれる戯画的な世俗の画題も、江戸時代中期を過ぎると、後に述べるように、大津絵節にうたい込まれた10種類のものに限定されたものとなってしまい、芸術的な新鮮味とユーモアの香りも徐々に失われていったと評されている。
大津絵節の起りが、元禄時代の終り頃と考えられていることについては、先に述べた通りであるが、江戸後期から明治にかけて全国的に大流行した大津絵節は、江戸時代中期の安永・天明頃(1772~1788)より歌い始められ、江戸時代後期の文化・文政年代を過ぎて、嘉永年間(1848~1853)に大流行となり、その流行が幕末・明治に及んだと考えられる。
江戸時代後期になって定ってくる大津絵の図柄10種は、1「外(げ)法(ほう)梯(はし)子(ご)剃(ぞり)」、2「雷と太鼓」、3「鷹匠」、4「藤娘」、5「座頭」、6「鬼の念仏」、7「瓢箪(ひょうたん)鯰(なまず)」、8「槍持(やりもち)奴(やっこ)」、9「釣鐘弁慶」、10「矢の根五郎」であるが、この画題と文化末・文政初年(1818)ごろのものと考えられる『守貞謾稿』所載の大津絵節の元歌10曲の題名とは、以下に記すように完全に一致している。なお、文化4年(1807)刊『弦曲粋弁当第四編』に記されている「大津の名物、二上り」の7種は、『守貞謾稿』の1から7までに、これまた完全に一致する。『守貞謾稿』は、著者が、「元章に因て名と」したもの、つまり、元の歌詞に基づき、要約して名づけたもので、内容的にやや理解しにくいものとなっているが、それにくらべると『弦曲粋弁当』の方は、幾分分かりやすいものとなっていると思われるので、1~7については、『守貞謾稿』の「名」に続けて、括弧を施し、『弦曲粋弁当』の「名」を記しておくことにする。
1. げほうはしごずり(げほう(外法)はしご(階子)そり(剃))
2. かみなり太鼓でつりをする(かみ(神)鳴たいこ(太鼓)はつる(釣)べ(瓶)とり(取))
3. おわか衆は鷹をすへ(前髪(まひかみ)はたか(鷹)をもつ)
4. ぬりがさおやまはふじの花(ぬり(塗)が(笠)さおやまは(女方)ふちの(藤)は(花)な)
5. 座頭のふんどしに犬わんわんつけァびつくりし杖をばふり上る(ざ(座)とうの(頭)ふんど(褌)しにいぬ(犬)つけば(附)ぎや(仰)うてん(天)し杖(つえ)をばふりあげる(振上))
6. あらきの鬼もほつきして鉦しゆもく(あらき(荒気)のおにもほ(鬼)つき(発気)してかね(鉦)しゆもく(撞木))
7. ひやうたんなまずをおさへます(ひゃ(飄)うたん(箪)な(鯰)まずをおさ(押)へます)
8. 奴(やっ)コの行れつ
9. 釣がね弁慶
10. 矢の根五郎
この画題と曲名の一致は、絵は絵としていかに有名であったか、また、歌は歌として、いかに盛んに歌われたかを物語っているわけであるが、こうした風調を作り出す大きな要因となったものは、やはり、大津絵を題材とした歌舞伎の舞踊曲だったと考えられる。舞台の襖(ふすま)または掛軸の大津絵から抜け出して踊るという趣向のもので、安永7年(1778)市村座の『大津絵姿(すがたの)花(はな)』では、藤娘・座頭・槍持奴の所作事がなされ、文政9年(1826)9月、中村座の『歌(か)へすがへす余波(なごりの)大津絵』では、藤娘・座頭などの五変化舞踊があり、明治4年(1871)の市村・守田両座合併興行の『名大津画劇交(なにおおつえりょうざのまぜ)張(はり)』では、大津絵の人物、大黒・座頭・奴・若衆・藤娘など8人が、大津絵どおりの拵(こしらえ)で、襖絵から抜け出て、シヌキ(仕拔 歌舞伎の殺陣(たて)の用語、立廻りとも)の踊をする。変化舞踊ではなく、シヌキが珍しいといわれている。なお、人形浄瑠璃にも、大津絵絵抜けと呼ばれる景事の曲名があり、文化7年(1710)9月の吉田辰造の『見(み)直(なおして)やはり七変化(ななばけ)』以来、大津絵の変化物として盛んに演じられたことが知られる。
以上見てきたように、結局は、世をあげての大津絵の愛好が、大津絵節の大流行をももたらしたのだといわざるをえないが、肝心(かんじん)要(かなめ)の大津絵節の歌詞は、実は、先にあげた元歌の替歌では必ずしもなかったのである。勿論、元歌の10曲の中のどれかを踏まえているものもないわけではないが、その比率は大変低く、主力は、当世の手近な恋の噂や諸々の出来事、あるいは何々尽しといったもので満たされていた。まさに、時代の流行歌集だったといえばよかったのである。
いま、ここに影印で掲げる版本大津絵節の18点の歌集によって考えてみても、大津絵節という名は、時代の流行歌の歌詞を集めて一冊の版本として出版するための一つの枠組み、一つの形式となっていたといった方がわかりやすりのかもしれない。大津絵の画題10種の内のどれかを色刷で描いた表紙を施すことでもって、あるいは、序文中に、大津絵の語を用いる、「ころばぬ先の大津絵」、「開化の時に大津画ぶし」といった具合に表現することで、または、口絵等に、「大津八丁札之辻」の「名物大津画所」の看板を掲げた店を、挿絵に描くことなどによって、かろうじて大津絵節であることを示しているといえるように思う。当然のことながら、出版元も、近江の大津ではなく、江戸・東京、大坂だったことが納得できるのである。
大津絵節の版本は、すでに述べたごとく、中本あるいは横小本で、1冊が5・6丁から20丁程度の小冊子で、例外も勿論あるけれども、原則として半丁に一曲の歌詞を収め、空白部には積極的に挿絵を入れることを基本として編集されたものであった。
[参考文献]
市場直次郎著『廃頽大津絵節』
昭和3年 東京発藻堂書院刊
(2004.3.10 文化教育学部教授 井上敏幸記)