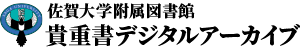津島日記とその関連書の解説
著者および『津島日記』について
文化八年(一八一一)、草場珮川(天明八年〈一七八八〉正月七日生、慶応三〈一八六七〉年十月二十九日没、享年八十歳)は、その師である古賀精里が幕命を受けて朝鮮通信使応接のため、対馬に赴くに随行した。その渡海の途中の五月朔日から、応接の任を終えて七月四日に対馬を発つまで、約二ヶ月間の見聞を記したのが、本『津島日記』である。
珮川、名は韡(さかえ)、字は棣芳(ていほう)、通称は瑳助(さすけ)、珮川(後に佩川)はその号である。肥前多久の人。二十三歳で江戸の昌平黌に学び、精里に師事する。のち多久侯に仕え、佐賀藩儒となり、藩校弘道館教授に任じた。詩集に『佩川詩鈔』(嘉永六年刊四巻四冊)があり、当時の高名詩人の作を集めた『文久二十六家絶句』(文久二年刊三巻三冊)にもその詩が採られ、また諸家の詩文集に多く序跋・評語を寄せるなど、詩人としても高い評価を得ている。晩年、こうした詩人としての盛名を得たことは、青年時に韓使と筆談応酬した実績による処が大きい。
その意味において『津島日記』は、儒学者としてあるいは詩人としての第一歩を踏み出そうとする、珮川の気概に満ちた記念碑的著述であると言える。その執拗なまでの記述は、少年時より学んだ南蘋流の画技を奮った挿絵とも相俟って、本書を易地行聘の式礼・幕末対馬藩の風俗を知るうえでの貴重な史料たらしめており、はやく、その全影印が『影印本 津島日記』(昭和53 財団法人 西日本文化協会)に収められ、日韓交流史の観点に主眼をおいた長正統氏による詳細な解題が付されて刊行された。そこでは『津島日記』諸本として、(イ)珮川の後孫で京都市在住の草場典夫氏所蔵本(写本三巻三冊)、(ロ)佐賀市在住の野中万太郎氏所蔵本(写本三巻三冊)、(ハ)京都大学所蔵本(写本二巻附図一巻三冊)の三種を挙げている。(イ)は、すなわち影印本の底本であり、長氏の解説によれば「珮川が手もとにおいて推敲の用に供していたもの」であり、(ロ)(ハ)は、基本的に草場本の転写本とされるものである。
諸本と小城文庫本との関係
先に、(ロ)野中本・(ハ)京都大学本は、基本的に(イ)草場本の転写本であると記したが、野中本と草場本との関係は、少し複雑なようである。長氏の解説を要約すれば、両者の関係はおよそ次のようになる。
すなわち、草場本には、一応の草稿が成ったのち、「大幅な抹消や書きこみもなく、しかも一連の稍やわらかみのある同一の筆跡で浄書して」差し替えた部分が上中下巻を通して見られるが、野中本上中巻は、この差し替え部分を生かしたかたちで書写がなされているのに対して、下巻は差し替え部分とは異なる本文が散見される。長氏はこの点に関して、野中本上中巻は、草場本上中巻における差し替え浄写が終了したのちに書写され、野中本下巻は、草場本下巻の差し替え浄写がなされる以前に書写されたと推定されている。
ここに紹介する小城本は、影印本によって草場本と比較してみると、野中本を実見しない今、断言することはできないが、その書写状況はちょうど野中本に等しいと思われる。すなわち、小城本の二丁表~七十六丁表は、草場本上中巻における訂正、差し替え浄書の部分をことごとく生かした書写がなされるが、小城本の下巻、特に九十六丁表~百三丁裏は、草場本とは著しく異なる本文をもっているのである。ならば、小城本と野中本とは全く同時期の書写に関わるのかと言えば、そうとも断言できない。何故なら野中本は、各巻冒頭に目次を置き、本文に丁数が付されるなど、長氏は「草場家本にくらべ、よりととのった体裁」であることを評価されたのであるが、対して小城本は上巻にのみ目次を置き、中下巻のそれを欠いているからである。あるいはその書写は野中本よりやや先んじるのかも知れないが、これも精査を経ない今、断言は避けるべきであろう。
文政元年五月十一日の珮川の日記には「撰在島日記三冊、更稿已三次」と見え、『津島日記』には、この時点で既に三度の推敲が重ねられていたこと、すなわち可能性としては三種類の本文が存在し得ることを知るが、小城本の出現は、野中本と同様に草場本以前の『津島日記』本文を提供してくれるという点にその意義を見出すことができよう。
小城鍋島文庫本の特記事項
その他、小城本に関して特記すべきは、『日記』上巻と下巻との間に、古賀精里編『後師録』が置かれていることであろう。本書は『国書総目録』(昭38~51 岩波書店)に就くと、所蔵元を「旧三井鶚軒」として、写本一冊の篠崎小竹校訂本が検索される。即ち、これは戦災で焼失、あるいはその他の理由で所在不明の書物である。また『古典籍総合目録』(平2 岩波書店)にも補足情報はなく、解題者も現時点において他所に本書が所蔵されるを知らない。従って、次に精里序文の全文を掲出して、本書の編集経緯および概要を窺っておく。
韓人ノ問答書 上木サルヽコト数十種ナリ。而シテ我 富嶽ヲ談ズレバ則チ、彼金剛ヲ以テシテ之ヲ厭ヒ、我 其ノ広裏ヲ問ヘバ則チ、二万里ヲ以テシテ之ヲ詫ブ。児女ノ迷蔵ノ戯ニ殆カラズヤ。邦儒 多ク其ノ窠臼ニ堕シテ、白石ヲ甚ダシト為ス。余 閑中、其ノ語ノ或ハ能ク人ヲ惑ハス者ヲ挙ゲ、草場、樋口ノ二生ヲシテ之ヲ駁セシム。敢ヘテ前輩ヲ紜摭スルニ非ズ。所謂、前事ノ忘レザルハ後事ノ師ナリ。旧轍ヲ鑒ミテ復タトハ蹈マザラント欲スルノミ。 (原漢文)
即ち、本書の編集目的は、それまでに刊行されている韓使との筆談集に見える「能ク人ヲ惑ハス者」、つまり誤謬を質すことにあり、精里は、珮川および樋口淄川(珮川とともに対馬に随行した人物)にその執筆を命じたのである。本書が編まれた背景には、『津島日記』下巻に
抑、国家恩信ヲ以テ大賓ヲ礼待セラレルノ本意ニ隨ヒ、以前ノ如ク主客垂角不遜ノ光景ニ到ラザルヤウ、林夫子ヲ始メ、此タビ予ジメ深ク心ヲ用ラレ、東里先生及余等ニ命ゼラレテ擬答擬問後師録ナドノ著述アッテ、前古ヲ鑑ミテ【小字双行 ・前年ノ筆語ニ国体ヲ弁ヘズ妄リニ論ジテ、公事ヲ妨ゲ、彼ニ佞シテ邦俗ヲ謗ル等ノコトアリ】後来ヲ戒メ、永ク文翰応接ノ規則ヲ立ラレタリ。
とあるように、韓使との筆談、いわば外交の席での国体に係わる不用意な発言を戒める意図があるようである。珮川・淄川が批判の対象として扱った「韓人ノ問答書」は、宮瀬龍門『龍門先生鴻臚傾蓋集』(寛延元年刊)、前田純陽『対麗筆語』(延享五年刊)、林鳳谷『韓話応酬』(内閣文庫蔵『韓館唱和』〈写本三巻続三巻別集一巻七冊〉、宝暦十四年成あたりを指すか)などであり、それらから珮川が二十四条、淄川が三十一条にわたって論駁を加えている。
(大庭卓也)