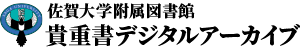浮世草子の解説
天和二(一六八二)年刊の井原西鶴の処女作『好色一代男』によって、それまで京都中心に行われていた啓豪・教訓的な仮名草子と一線を画して以来、十八世紀の半ばをすぎた宝暦・明和(一七五一〜一七七二)のころまでの約八十年間、上方中心に行われた現実主義的で娯楽的な町人文学を浮世草子という。
名義
元禄七年(一六九四)刊の『西鶴織留』の北条団水序に、「西鶴生涯のうち序作する所の仮名草子」とあるように、西鶴当時はまだ彼の作品も仮名草子とよばれていた。その内容に即して浮世草子という名目が現われたのは、西鶴の没後十年余を経過した十八世紀のはじめ、宝永年間(一七〇四〜一七一一)からである。「浮世」の意味は、すでに寛文期(一六六一〜一六七三)の仮名草子『浮き世物語』の序で、著者の浅井了意が語っているように、仏教の無常観と動乱の現実にもとずく中世的な「憂世」の概念が、近世に入って経済生活を確立した現実的で享楽的な上方町人の生解釈によって、浮きに浮いて慰む「浮世」と変ったのである。西鶴の作品にも「浮世」と冠した熟語が数多く散見している。浮世絵・浮世小紋などは当世風といういみであるし、浮世女・浮世比丘尼・浮世寺・浮世狂いなどは、享楽的ないし好色的という意味である。したがって浮世草子とは、現代の世相・風俗を何くれとなく取り上げて描いた娯楽的な小説と考えればよい。しかし何しろ一世紀近くも行われているので、現代的とは言えない作風もあらわれている。
種類
題材的に大別すれば、すでに西鶴の諸作にその原点が備わっている。遊里や一般町人社会の愛欲を主題とする好色物、経済生活を主題とする町人物、武家生活を扱った武家物、諸国の怪奇談を編集した伝奇小説、人々の耳目をひく巻説を扱った実話小説、類型的人間像を刻む気質(かたぎ)物などである。
書型
仮名草子以来の美濃紙二つ折の大本を主とし、それに半紙本・横本(枕本)の新形式が、西鶴の没後に加わっている。さらに西鶴当時の貞享・元禄期(一六八四〜一七〇四)には、主として西鶴の地元の大阪で刊行されているが、西鶴没後の元禄末年、十八世紀のはじめ頃からは、大板元の八文字屋を中心に、主として京都で制作・刊行されるようになった。
展開
西鶴の諸作品によって現代的な娯楽性と商品価値を確認された浮世草子は、西鶴の没後いよいよ商業ベースに乗り、大衆文学化の一途をたどりはじめた。西鶴の没後しばらく、大阪の本屋作者西沢一風を中心に群小作者が輩出し、『好色万金丹』(元禄七年)、『好色年男』(同八年)、『好色小柴垣』(同九年)といった、商品価値の高い艶笑小説がひとしきり行われた。江戸でも、桃林堂蝶麿が、『好色赤烏帽子』(元禄八年)、『好色艶(つや)虚無僧』(同九年)などの艶笑小説を、宝永初年(一七〇四〜)までに十四、五部も刊行している。もちろん問題意識や社会的視点を有する西鶴の好色本とちがい、これらはおおむね興味本位の艶笑譚である。
『日本古典文学大辞典』,岩波書店,「浮世草子」項より