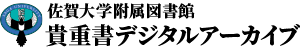葉隱の解説
一、解説
『葉隱』は、「武士道と云ふは、死ぬ事と見付けたり」(巻一・2)という一文によって知られ、 この一文によって「日本武道第一の書」(栗原荒野『校註葉隱』解説 昭和15年刊)、あるいは「どこを切っても、鮮血のほとばしるやうな本」(古川哲史 岩波文庫『葉隱』解説 昭和32年刊)と 評されてきた本であることは周知のとおりである。だが、『葉隱』の説く「武士道」が、武闘を意味する「武道」だけをいうのではなく、「奉公」、即ち「日々の勤め」をも含めて問題としたものであること、また、「死ぬ事」という言葉も、実際に命を断つことではなく、「心組(こころぐみ)」、つまり、「心の持ち様」を説いたものであることに注意したいのである。
『葉隱』が、平和時における侍の、人間としての心の持ち様を説いた本であったということになれば、人間いかに生きるべきかを問い求めている現代人にとっても、大いに資するところのある本だというべきであろう。
この『葉隱』が、江戸時代から明治末年まで広く読まれたことは、多くの写本が残されていることに端的に示されており、現存する写本の数は、四十点を越えるだろうといわれている。いま紹介している佐賀大学の小城鍋島文庫にも、この九冊本以外に六巻四冊(巻一・二、七・ 八、十一欠)の水町本、また一冊本の『葉隱抜書』があって、小城藩においても、やはりよく読まれていたことが知られるのである。
ところで、『葉隱』は、出版されることなく、明治末まで、次々と転写される形で伝えられてきたのであるが、肝心要の、『葉隱』原本の所在や、その成立時期については、すべてが不明のままだというのが一番正しい言い方だといってよいであろう。こうした中で、成立時期については、現在、『葉隱』序文冒頭の日付「宝永七年(1710)三月五日」と、一部の写本の奥に記されている「享保元年(1716)九月十日」という日付をもとに、初会の日から七年を経た享保元年に『葉隱』は成立したとする説が、通説となっている。だが、「享保元年九月十日」という日付が、どのような根拠に基づくものなのか、実は全く不明のままに、用いられている点に大きな問題があるといわねばならないのである。また、内容の面から見てみても、『葉隱』の成立が単純に「享保元年」でありえないことは、巻五の書き入れの中に「元文五年(1740)」の年号が出てくることから明らかである。ということになれば、問題は、『葉隱』の成立そのものをどのように考えるかという、最も基本的な問いに立ち帰って考えなければならないことになろう。
そこで、現存の『葉隱』の基本的構成を見てみると、巻一・二に、常朝が直接陣基に口述した話が集められ、そのことを暗示するものとして、巻一・二の内題の下に「教訓」という言葉が置かれたと考えられる。そして、巻三・四・五の三巻には、[A]直茂から勝茂・光茂・綱茂に至る代の藩主の逸話、巻六には、[B]佐賀藩に古くから伝えられる話、巻七・八・九には、[C]藩士達の評判、続いて、巻十には、[D]他の藩の噂が集められ、最後の巻十一には、[E]これまでの十巻に収められなかった話が、まとめられたのだと考えられる。巻一・二の「教訓」の条々には、確かに常朝の語りが感じられるが、巻三から巻十一までには、そうした感じはなく、むしろ、常朝以外の人々の話、または、残存する歴史資料等に基づき、かつ、[A]~[E]の分類意識に添って編集された感じが強いのである。[A]~[E]の中に常朝が語った話が、全く無いわけではないのかも知れないが、常朝の話というよりも、陣基が、常朝の話をよりよく理解してもらうための資料として、常朝没後も、関連する話や資料の蒐集を続け、分類し、編集していたといってよいように思う。こうした編集過程が想定されてよいとすれば、陣基は、寛延元年(1748)まで生きていたわけで、『葉隱』の中に、「元文五年(1740)」の記事があったとしても不思議ではなかったことになる。
では、この小城鍋島文庫本の成立時期はいつ頃だったかという問題であるが、写本に奥付などはなく、そうした年次を推定させる手懸りとなりうるものも一切見出しえない。従って、小城本と同じ系統に属するとされる鹿島本との比較、あるいは、小城鍋島文庫に蔵されている二つの『葉隱』、水町本と一冊本との関係、さらには、『葉隱』から三十二条の抜書を収めている『古今雑事集篇』の成立年次等々を勘案することで、大よその成立年次を考えてみることにする。
現在、『葉隱』の諸本は、鹿島本系、小山本系、孝白本系の三つに分類されるとされ(「『葉隱』 の諸本について」佐藤正英氏日本思想大系『三河物語 葉隱』解説 昭和49年 岩波書店)、小城本は、鹿島本系だといわれている。確かに両本は、付録共に十一巻の仕立てであること、全巻の条目が一致すること、また、巻五の末の方二十六条が、後に追加されたものであることが、共に「従是末百武氏書伝写」とあってわかること、さらに、巻六の巻尾に、一つ書きなしに、「御代々御判物」として、直茂・勝茂(四)・忠直・光茂・綱茂・吉茂の花押、都合九つを掲げていることにおいて、同系統であるといって間違いない。ただし、両者は、どちらがどちらを写したといった関係にあるのではなく、共に先行する写本によって別々に写されたものであることが、小城本の欄外朱書「別之字一本ニ作萬(別の字一本に萬に作る)」(巻五)、「披一作扱(披一つに扱に作る)」「場一作働(場一つに働に作る)」(巻八)、「に一本ニ作上(に一本に上に作る)」(巻十)で指摘されている文字「萬」「扱」「働」「上」が、鹿島本では、全てその通りの文字になっていることによって知られる。しかしながら、このことは、小城本が鹿島本を写したことを意味しない。鹿島本には、意味不明の書写がなされている箇処が多いが、小城本には、そうした箇処は少なく、文意もよく通っているからである。すでに述べたごとく、両者はやはり別々に、それぞれの親本によって写されたのであり、小城本の校訂に用いられた「一本」も、恐らく、鹿島本なのではなく、鹿島本が親本としたであろう一本、あるいは、その親本よりも先行する鹿島本系列の一本だったと見て間違いないであろう。いま述べたことを図示してみれば、
→〈?〉→〈?〉→〈鹿島本親本〉→ 鹿島本
葉隱原本→〈鹿島本原本〉
→〈?〉→〈?〉→〈小城本親本〉→ 小城本
のようになる。「葉隱原本」と、現存の鹿島本・小城本の間には、〈 〉で示したように、最小限 三本、多い場合には、四本、あるいは五本、またそれ以上の写本が存在したことが考えられてよいであろう。これらの三本、あるいは四・五本、またそれ以上の不明本の探索が今後の研究に期待されることになる。
最後に、小城本の書写年次について考えておくことにする。小城鍋島文庫の別本『葉隱聞書』、 いうところの水町本の奥付には、「文化八年秋 水町菅原忠成 六十一歳写」とあって、この水町本の書写年次は文化八年(1811)であることがわかる。この水町本の本文は、鹿島本系のそれであるが、読み易く文章を改めた部分と誤脱が多く、決して善本とはいえないものである。また、巻六末尾の「御代々御判物」の部分には、「一つ書き」が加えられ、代藩主の花押は、隆信・鎮賢・政家が加えられて十六となり、さらに、隆信・政家・直茂の「御印」四顆が加えられており、『葉隱』の一条目が、この時点においてまた一つ新たに出来上っていることが知られる。とすれば、小城本の成立は、少なくとも文化八年以前だったと見て間違いないことになろう。小城鍋島文庫のいま一つの『葉隱』資料である『古今雑事集篇』六巻三冊は、第六代藩主直員(なおかず)の長男直嵩(七代は弟直愈が継ぐ)の、安永三年(1774)から、安永九年(1780)にかけての読書の抜書である。この中に、『葉隱』からの引用三十二条があるが、直嵩は、恐らくこの小城本『葉隱』から抜書したものかと考えられる。しかしながら、『古今雑事集篇』引用の『葉隱』の条々は、省略の多い簡略なもので、どの写本からの引用であるかを判断することは不可能であるが、いま一つの『葉隱抜書』一冊は、『葉隱』の巻一・二・三から抜いた二十二条でもって、新たに『葉隱抜書』巻之一を編もうとしたものである。序文に相当する「宝永七年三月五日初会」(小城本は「初会参会」とある)と、奥書にあたる第一冊前遊紙裏の四行の書付「此始終十一巻追而火中すべし云々」の一条とが、小城本同様に『抜書』の冒頭に置かれており、この『抜書』も、あるいは、この小城本を手元に置いてなされたものだったかと推測される。そして、この『葉隱抜書』一巻 を編んだ人物も、直嵩あるいは直嵩の末弟直熙ではなかったかと考えられる。というのも『古今雑事集篇』『葉隱抜書』の両書にある蔵書印「曲肘亭」「叢桂館蔵書」が、鹿島藩の中川文庫にある蔵書印に同じだからである。つまり、鹿島藩主を継いだ直熙が、兄の遺書類を大切に所蔵し、 後鹿島藩主の養子となった折に、その一部を持っていったことも考えられるからである。以上述べてきたことが首肯されるとすれば、この小城本は、直嵩の旧蔵書であり、少なくとも安永三年(1774)には、手元に置かれていたといってよいことになろう。直嵩が生まれたのが、宝暦三年(1753)であったことを考えてみれば、この小城本を入手した時期も、十年後の明和元年(1764)をさほど遡ることはないかと思われる。だとすれば、本書を手元に置いた時期、つまり、家臣達に命じて書写させたであろう時期は、ほぼ、明和元年(1764)から安永二年(1773)にかけての十年間であったかと考えられる。いま、家臣達に書写させたであろうといったが、それは、小城本の書写態度が、鹿島本と比べた場合、適度な緊張感を持って書写された、優れた写本だといってよかったからである。(井上敏幸)